七五三のお参りでいただく「絵馬」。
せっかくなら正しい書き方で、心を込めて願いを残したいですよね。
でも「どう書けばいいの?」「どんな願いを書いたらいい?」と迷う方も多いはずです。
この記事では、七五三における絵馬の意味や基本的な書き方をわかりやすく解説し、実際にそのまま使える短文例文とフルバージョンの例文をたっぷり紹介します。
さらに、親子や祖父母と一緒に書く工夫、注意点、奉納や自宅での保管方法まで徹底的にカバー。
読み終えたときには「これなら自信を持って絵馬を書ける」と思える内容になっています。
七五三という節目を、家族みんなで心を込めて彩るための参考にしてください。
七五三で絵馬を書く意味とは?
七五三で絵馬を書くことには、単なる「儀式以上の意味」があります。
この章では、七五三という行事と絵馬の結びつき、そして親子で願いを込めることの価値を解説します。
七五三の行事と絵馬の関係
七五三は、3歳・5歳・7歳という節目にお子さまの成長を神様に感謝し、これからの健やかな人生を祈願する日本の伝統行事です。
かつては子どもが無事に成長することが難しかった時代もあり、七五三は「ここまで生きてくれてありがとう」と「これからも元気でいてね」という二つの思いを込める大切な節目でした。
絵馬はその思いを「形に残す手段」であり、言葉を板に刻むことで祈りを神様へ届ける役割を持っています。
| 七五三の意味 | 絵馬の役割 |
|---|---|
| 成長への感謝 | 感謝の言葉を神様に伝える |
| これからの健康祈願 | 願いを具体的に残す |
| 家族の幸せ祈願 | 家族全員の想いを形にする |
親子で絵馬を書くことの価値
親が願いを込めるだけでなく、子ども自身が絵馬に関わることはとても大切です。
たとえ字がまだ上手に書けなくても、線や丸の落書きであっても「自分で書いた」という体験自体が尊い記念になります。
親子で「どんなお願いをしようか?」と話し合う時間は、学びや会話のきっかけになり、後々まで残る思い出となります。
つまり、七五三の絵馬は「願いを込める行為」と「家族の心を結ぶ儀式」なのです。
七五三の絵馬の基本的な書き方
いざ絵馬を手にすると「どこに何を書けばいいの?」と迷うこともありますよね。
ここでは、初めての方でも安心して書けるように、基本的な流れと書き方のコツを解説します。
書く位置と正しい流れ
絵馬には表と裏があります。
一般的には表面に願いごと、裏面に名前や日付を記入します。
願いごとは大きめの字で、はっきりと書くのがポイントです。
子ども本人に書かせる場合は、文字が拙くても大丈夫です。
素朴な字や絵は、そのまま「心のこもった証」になるからです。
| 絵馬の面 | 書く内容 |
|---|---|
| 表 | 願いごと(例:「元気に育ちますように」) |
| 裏 | 名前・ふりがな・年齢・日付 |
名前・日付・年齢の記載方法
神様に願いを届けやすくするために、願いごととあわせて名前や年齢を記入するのが一般的です。
特に子どもの場合、ふりがなを書き添えるとわかりやすいでしょう。
また日付を入れると、後から見返したときに「このときに書いたんだな」と家族の思い出にもなります。
ただし、近年は個人情報を守るために、フルネームや住所は避ける方も増えています。
「下の名前だけ」「都道府県まで」など簡略化しても、ご利益に影響はありません。
縦書き・横書きや使用するペンのポイント
絵馬は縦書き・横書きどちらでもOKです。
昔ながらの雰囲気を出したいなら縦書き、現代風に気軽に書きたいなら横書き、と好みに合わせて大丈夫です。
使用するペンは、雨風に強い油性ペンがおすすめです。
水性ペンだとにじんでしまう可能性があるので避けた方が安心です。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 文字方向 | 縦書きでも横書きでも問題なし |
| ペン | 黒色の油性ペンが最適 |
| 個人情報 | 名前は下の名前だけでも十分 |
七五三でよく使われる願いごとの種類と例文
「どんな願いを書けばいいのかな?」と迷う方のために、七五三でよく見られる願いごとをテーマ別に整理しました。
ここでは短い例文と、実際にそのまま書けるフルバージョンの例文を両方紹介します。
健康を願う例文(短文+フルバージョン)
七五三の絵馬で最も多いのは「健康祈願」です。
病気やケガをせず元気に育ってほしい、という親の願いが込められます。
- 「〇〇がこれからも元気に育ちますように」
- 「毎日笑顔で過ごせますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ・ふりがな)がこれからも健康で、すくすく成長しますように。 令和〇年11月15日 満5歳」
勉学や成長に関する例文(短文+フルバージョン)
小学校入学や新しい環境に向けての「学び」や「成長」を祈る言葉も人気です。
- 「小学校でも勉強を楽しめますように」
- 「いろいろなことに挑戦できますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ)が小学校に入っても楽しく学び、立派に成長しますように。 令和〇年11月 7歳」
人間関係や心の豊かさに関する例文(短文+フルバージョン)
友達との関わりや、優しさを持ってほしいという心の成長への願いもよく書かれます。
- 「友達と仲良く遊べますように」
- 「思いやりのある子に育ちますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ)が感謝の心を忘れず、友達や家族と仲良く暮らせますように。 令和〇年 七五三」
家族全体の幸福を願う例文(短文+フルバージョン)
最近では、子どもだけでなく家族全員の幸せを祈る方も増えています。
- 「家族みんなが健康で過ごせますように」
- 「笑顔のあふれる毎日になりますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇と家族みんなが、これからも健康で幸せに暮らせますように。 令和〇年11月 吉日」
| 願いの種類 | 短文例 | フルバージョン例 |
|---|---|---|
| 健康 | 元気に育ちますように | 〇〇がこれからも健康で成長しますように。令和〇年〇月〇日 |
| 学び | 勉強を楽しめますように | 〇〇が楽しく学び立派に成長しますように。満7歳 |
| 人間関係 | 友達と仲良く遊べますように | 〇〇が感謝の心を持ち、友達と仲良くできますように |
| 家族 | 家族みんなが健康で過ごせますように | 家族全員が笑顔で幸せに暮らせますように |
七五三でよく使われる願いごとの種類と例文
「どんな願いを書けばいいのかな?」と迷う方のために、七五三でよく見られる願いごとをテーマ別に整理しました。
ここでは短い例文と、実際にそのまま書けるフルバージョンの例文を両方紹介します。
健康を願う例文(短文+フルバージョン)
七五三の絵馬で最も多いのは「健康祈願」です。
病気やケガをせず元気に育ってほしい、という親の願いが込められます。
- 「〇〇がこれからも元気に育ちますように」
- 「毎日笑顔で過ごせますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ・ふりがな)がこれからも健康で、すくすく成長しますように。 令和〇年11月15日 満5歳」
勉学や成長に関する例文(短文+フルバージョン)
小学校入学や新しい環境に向けての「学び」や「成長」を祈る言葉も人気です。
- 「小学校でも勉強を楽しめますように」
- 「いろいろなことに挑戦できますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ)が小学校に入っても楽しく学び、立派に成長しますように。 令和〇年11月 7歳」
人間関係や心の豊かさに関する例文(短文+フルバージョン)
友達との関わりや、優しさを持ってほしいという心の成長への願いもよく書かれます。
- 「友達と仲良く遊べますように」
- 「思いやりのある子に育ちますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇(なまえ)が感謝の心を忘れず、友達や家族と仲良く暮らせますように。 令和〇年 七五三」
家族全体の幸福を願う例文(短文+フルバージョン)
最近では、子どもだけでなく家族全員の幸せを祈る方も増えています。
- 「家族みんなが健康で過ごせますように」
- 「笑顔のあふれる毎日になりますように」
フルバージョン例文
- 「〇〇と家族みんなが、これからも健康で幸せに暮らせますように。 令和〇年11月 吉日」
| 願いの種類 | 短文例 | フルバージョン例 |
|---|---|---|
| 健康 | 元気に育ちますように | 〇〇がこれからも健康で成長しますように。令和〇年〇月〇日 |
| 学び | 勉強を楽しめますように | 〇〇が楽しく学び立派に成長しますように。満7歳 |
| 人間関係 | 友達と仲良く遊べますように | 〇〇が感謝の心を持ち、友達と仲良くできますように |
| 家族 | 家族みんなが健康で過ごせますように | 家族全員が笑顔で幸せに暮らせますように |
親子や祖父母と一緒に書く工夫
七五三の絵馬は、子ども本人だけでなく、親や祖父母が一緒に関わることでさらに思い出深いものになります。
ここでは、それぞれの立場での工夫やポイントを紹介します。
子どもが自分で書く場合のポイント
子どもが字を書ける年齢なら、自分で書かせてみましょう。
たとえ丸や線のような落書きでも「自分で書いた」という体験が何よりの宝物になります。
親はそばで「どんなお願いをしたい?」と声をかけるだけで十分です。
お子さまが考えた言葉をそのまま残すことで、将来振り返ったときに心温まる記録となります。
親が代筆する場合の工夫
まだ字が書けない子どもの場合は、親が代筆しても問題ありません。
その際は、単に「親の言葉」ではなく、子どもの気持ちを代弁することを意識しましょう。
「〇〇が好きな遊びをこれからも楽しめますように」など、子どもが日常で話している言葉を盛り込むとリアルで温かみのある絵馬になります。
祖父母が願いを込めるときの言葉選び
祖父母が書く場合は、親とはまた違った視点から願いを込められます。
「これからも健康で長生きしてね」「周りの人に愛される人になりますように」など、人生経験に基づいた温かい言葉が特徴的です。
子どもにとっても、祖父母からの願いは家族の歴史を感じられる贈り物になります。
| 書き手 | 工夫のポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 子ども | 自由に書かせる | 丸や線も「本人の願い」として大切に |
| 親 | 子どもの言葉を代筆 | 「好きな遊びを楽しめますように」 |
| 祖父母 | 人生経験を込める | 「周囲に愛される人になりますように」 |
七五三の絵馬を書くときの注意点
絵馬に願いを書くときは「自由でいい」とはいえ、少し気をつけたいポイントがあります。
ここでは、より良い形で願いを込めるための注意点を紹介します。
ネガティブな表現を避ける理由
「病気になりませんように」と書くよりも「健康に過ごせますように」と書いた方が前向きです。
否定形の願いは重く響いてしまうことがあるため、なるべく明るい表現を選びましょう。
ポジティブな言葉は読み返したときにも気持ちよく残ります。
個人情報を守るための工夫
昔は住所やフルネームを書くのが一般的でしたが、近年は名前だけ・下の名前のみで十分とされています。
住所を書く場合も「〇〇市まで」や「都道府県まで」でとどめると安心です。
神社によっては個人情報を隠せるシールを用意しているところもあります。
願いが届くかどうかは「心を込めて書いたかどうか」が大切なので、省略しても問題ありません。
神社ごとのルール確認
神社によっては「表に願い・裏に名前」と明示している場合や、縦書きが推奨されている場合があります。
また「黒色の油性ペンを使ってください」といった案内があることもあります。
不安なときは、社務所の方に確認して従えば安心です。
| 注意点 | 望ましい書き方 |
|---|---|
| ネガティブ表現 | 「病気になりませんように」→「健康で過ごせますように」 |
| 個人情報 | フルネームや住所は避ける/名前だけで十分 |
| 神社ごとのルール | ペン・書き方・奉納方法を事前に確認 |
奉納と保管の正しい方法
絵馬を書いた後は「神社に奉納する」「自宅で飾る」の2つの方法があります。
どちらを選んでも間違いではありませんが、それぞれの正しい方法を知っておくと安心です。
神社での奉納方法
神社には「絵馬掛け」と呼ばれる専用の場所があります。
書き終えた絵馬は、境内の絵馬掛けに紐をかけて吊るすのが一般的です。
神社によっては「絵柄を表にして掛ける」など指定があるので、案内を確認しましょう。
奉納することで神様に願いが託されると考えられています。
自宅での飾り方と保管の仕方
いただいた絵馬をすぐに奉納せず、自宅に飾る方もいます。
その場合は人の目線より高い清らかな場所に置くのが良いとされています。
神棚や床の間があれば最適ですが、リビングの棚などでも問題ありません。
他の授与品(お守りや破魔矢など)と一緒に飾るのも良い方法です。
返納やお焚き上げのタイミング
奉納した絵馬や、自宅に飾っていた絵馬は約1年を目安に返納するのが一般的です。
願いが叶ったときにも、感謝の気持ちを込めて返納します。
多くの神社では「お焚き上げ」という儀式で絵馬を処分します。
炎にくべることで「願いを天に届ける」とされ、気持ちよく新しい一年を迎えられます。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 神社で奉納 | 絵馬掛けに吊るす/案内に従う |
| 自宅で飾る | 目線より高い位置/授与品と一緒に |
| 返納 | 1年を目安/願いが叶ったときにも返納 |
七五三で授与される絵馬以外の品々
七五三では絵馬以外にも、縁起の良い授与品をいただくことがあります。
それぞれに意味があり、正しく扱うことでより良い祈願につながります。
千歳飴の意味と扱い方
千歳飴は七五三の代表的な授与品です。
「千歳」という言葉には長寿や健やかな成長の願いが込められています。
細く長い形状は「細く長く生きる」ことを象徴し、袋の鶴や亀の絵柄は縁起の良さを表しています。
食べ方に特別な決まりはなく、切って料理やお菓子に使う家庭もあります。
破魔矢やお守りの役割と保管方法
破魔矢(はまや)は邪気を払う矢として授与されます。
家に持ち帰ったら、神棚やリビングの高い場所に飾るのが一般的です。
向きは南や東向きが良いとされますが、厳密なルールはありません。
お守りは常に身近に持つことでご利益があるとされ、カバンやポーチに入れておくと良いでしょう。
どちらも1年を目安に返納し、新しいものを授かります。
| 授与品 | 意味 | 扱い方 |
|---|---|---|
| 千歳飴 | 長寿・成長祈願 | 食べて良い/切って料理にも使える |
| 破魔矢 | 魔除け | 高い位置に飾る/1年で返納 |
| お守り | 身を守る | 持ち歩くか高い位置に保管/1年で返納 |
まとめ|七五三の絵馬に願いを込めて家族の思い出に
七五三の絵馬は、単なる祈願のための道具ではなく家族の心を結ぶ大切な儀式です。
書き方に厳密な決まりはありませんが、願いをポジティブに表現し、心を込めて書くことが大切です。
また、短い願いだけでなく「名前・年齢・日付」を添えることで、未来に振り返ったときの大切な記録にもなります。
子ども本人の拙い字や落書きも、親子や祖父母の温かい言葉も、すべてが「その瞬間だけの思い出」です。
奉納しても自宅で飾っても構いませんが、返納のときには感謝の気持ちを忘れずに伝えましょう。
ぜひ七五三の節目に、世界で一つだけの絵馬を通じて家族の想いを形に残す体験をしてください。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 書き方 | 願い+名前+年齢+日付が基本 |
| 表現 | ネガティブは避けて前向きに |
| 関わり方 | 親子や祖父母と一緒に書くと良い |
| 奉納・保管 | 神社に奉納/自宅に飾るどちらもOK |
| 返納 | 約1年を目安にお焚き上げや返納 |


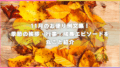
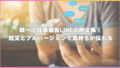
コメント