小学校の卒業式は、子どもたちの成長を祝い、未来へのエールを贈る大切な節目です。
祝辞を任されたとき、「どんな言葉を選べばいいのか」「どのくらいの長さで話せばいいのか」と悩む方も多いですよね。
この記事では、PTA会長・保護者代表・来賓など立場別に使える小学校卒業式の祝辞例文をわかりやすく紹介します。
そのまま読めるフルバージョン例文から、心に響く言葉の選び方、避けたいNG表現まで丁寧に解説。
“感謝と希望をまっすぐ伝える言葉”が、卒業生の心に残る最高の贈り物になります。
この記事を参考に、あなたらしい温かい祝辞を完成させましょう。
小学校の卒業式祝辞とは?目的と基本マナー
卒業式の祝辞は、子どもたちの成長を祝い、保護者や教職員への感謝を伝える大切な場面です。
ここでは、祝辞の基本的な意味や目的、そして話すときに心がけたいマナーについてわかりやすく解説します。
祝辞の意味と目的
小学校の卒業式で述べる祝辞には、3つの明確な目的があります。
それは「お祝いの気持ち」「感謝の言葉」「未来への励まし」を伝えることです。
祝辞とは、卒業という節目をみんなで喜び合い、新たな一歩を応援するための言葉なのです。
決して難しい表現を使う必要はありません。
大切なのは、心を込めてシンプルに伝えることです。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| お祝い | 卒業生の努力や成長をたたえる |
| 感謝 | 保護者・教職員・地域の支えへの感謝を述べる |
| 励まし | 新しい生活に向けての希望や応援の言葉を贈る |
祝辞に込める3つの気持ち(感謝・成長・希望)
祝辞の中で伝えたいのは、次の3つの気持ちです。
まず「感謝」。これは、先生方や保護者へのありがとうの気持ちです。
次に「成長」。卒業生が小学校生活で身につけた力を具体的に称えることです。
最後に「希望」。これから始まる中学校生活に向けた前向きな言葉を贈ります。
この3つがバランスよく盛り込まれている祝辞は、どんな立場の人にも好印象を与えます。
長さ・構成・話すときのマナー
小学校の卒業式祝辞は、長すぎず、わかりやすい言葉で構成することがポイントです。
一般的には3〜5分程度(原稿用紙2枚半〜3枚ほど)が目安とされています。
また、話すときの姿勢や声のトーンにも注意が必要です。
| ポイント | 具体的な注意点 |
|---|---|
| 話す速度 | 早口にならず、1文ごとに区切るように意識 |
| 視線 | 原稿を見すぎず、会場全体に目を向ける |
| 言葉遣い | 難しい言葉を避け、小学生にも伝わる表現を選ぶ |
祝辞は“伝える”よりも“届ける”もの。
聞く人の心に温かく残るように、一言一言を丁寧に語りましょう。
使いやすい!卒業式祝辞の基本テンプレート(構成例つき)
祝辞は、「何を、どんな順番で話すか」が整理されていれば、誰でも安心して準備できます。
この章では、基本構成の流れと、そのまま使えるフルバージョン例文を紹介します。
立場に関係なく活用できる内容なので、ぜひあなたの言葉に置き換えて使ってみてください。
祝辞の基本構成(導入・本文・結び)
卒業式の祝辞は、以下の3部構成で考えるとわかりやすいです。
| 構成 | 内容の概要 |
|---|---|
| 導入 | お祝いと感謝の言葉で始める |
| 本文 | 子どもたちの成長や思い出を具体的に述べる |
| 結び | 未来への励ましと感謝で締めくくる |
この順番を守るだけで、自然で心に残る祝辞になります。
【フルバージョン例文】誰でも使える完成形テンプレート
以下は、どの立場の方でも使いやすい汎用型のフル祝辞例文です。
全体で約3分を目安に構成してあります。
———
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
本日はこのように晴れやかな日を迎えられたことを、心からお祝い申し上げます。
また、今日まで子どもたちを支えてこられた保護者の皆様、そして温かく導いてくださった先生方にも、心より感謝申し上げます。
6年間という長い時間の中で、皆さんは本当にたくさんのことを学び、経験してきました。
勉強や行事、友達との協力、時にはうまくいかないこともあったでしょう。
それでも一歩ずつ努力を重ね、立派に成長された姿に、私たちは深く感動しています。
これから中学校へ進む皆さんには、新しい出会いや挑戦が待っています。
知らない環境の中で戸惑うこともあるかもしれませんが、小学校で培った優しさや思いやり、そしてあきらめない気持ちを忘れずにいてください。
失敗を恐れず、前に進もうとする姿こそが、これからの力になります。
最後に、保護者の皆様、先生方、地域の皆様に改めて感謝を申し上げます。
子どもたちの未来が明るく輝くものであるよう、心から願っております。
卒業生の皆さん、本日は本当におめでとうございます。
———
テンプレートを自分らしくアレンジするコツ
上記の例文をそのまま使うこともできますが、少しだけ自分の言葉を加えると、ぐっと温かみが増します。
| アレンジポイント | 具体例 |
|---|---|
| 学校の特色を加える | 「○○小学校の校庭で見た満開の桜のように」など |
| 地域らしさを取り入れる | 「○○市の冬の寒さに負けず元気に登校した皆さん」など |
| 児童の思い出を一言添える | 「運動会で見せた団結の力は忘れません」など |
「自分の目で見たこと」「感じたこと」を一言入れるだけで、祝辞が一気に“あなたらしい言葉”になります。
文章の型はそのままに、心からの想いを少し足すことがポイントです。
【立場別】小学校卒業式祝辞の例文集
ここでは、祝辞を述べる立場ごとに、雰囲気や長さを調整した実用例文を紹介します。
すべて3分以内で読める内容にまとめているので、あなたの役割に合わせて使ってください。
「自分の立場に合う言葉をそのまま使える」ことを重視した構成になっています。
PTA会長の祝辞(フォーマル&感動型)
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
本日は、保護者とPTAを代表して、皆さんの門出に心よりお祝いを申し上げます。
この6年間、皆さんはたくさんの経験を通して立派に成長されました。
行事の準備や運動会、学習発表会など、一つひとつの活動を仲間と協力しながらやり遂げた姿は、本当に素晴らしかったです。
これから進む中学校生活では、新しい出会いや挑戦が待っています。
どんなときも、自分を信じて、仲間を思いやりながら進んでいってください。
先生方、そして保護者の皆様にも深く感謝を申し上げます。
子どもたちを支え、見守り続けてくださったおかげで、今日という日を迎えることができました。
卒業生の皆さんのこれからの人生が、笑顔と希望に満ちたものになりますよう、心からお祈りしています。
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 格式を保ちながら温かい | 「感謝」「成長」「未来」の3要素をバランスよく配置 |
| 使う場面 | PTA会長・保護者代表のスピーチ |
保護者代表の祝辞(親しみやすい型)
卒業生の皆さん、そして保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。
保護者を代表して、心からお祝いの言葉を申し上げます。
今日までの6年間、子どもたちは多くの学びや経験を重ね、心も体も大きく成長しました。
初めてランドセルを背負って登校した日の姿が、今でも思い出されます。
毎朝元気に「いってきます」と登校していた皆さんが、こんなに頼もしく成長されたことが本当にうれしいです。
これからはそれぞれの道を歩み始めますが、小学校で培った友情や思いやりを大切にしてください。
先生方、これまでのご指導と温かいご支援に深く感謝申し上げます。
子どもたちの未来が、笑顔あふれる日々でありますよう願っています。
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 親目線のあたたかさ | 自分の子どもの思い出をさりげなく織り込む |
| 使う場面 | 保護者代表・謝辞の挨拶 |
校長先生・来賓代表の祝辞(格式と品格のある型)
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
本日はこのように盛大な卒業式を迎えられたことを、心よりお祝い申し上げます。
6年間の学びの中で、皆さんは知識だけでなく、人との関わりや社会のルールを学んできました。
先生方の熱心なご指導、そして保護者の皆様の支えがあってこそ、この日を迎えられたのだと思います。
これから進む新しい世界では、努力を重ねながら、自分の力で道を切り拓いていってください。
学び続ける姿勢と、人を思いやる心を大切にしてほしい。
皆さんの未来が輝かしいものであることを、心から願っています。
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 上品で簡潔 | 「努力」「感謝」「希望」を落ち着いた語調で伝える |
| 使う場面 | 校長先生・来賓代表・地域代表など |
児童代表(在校生・卒業生)のメッセージ例文
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
私たち在校生は、先輩方の姿から多くのことを学びました。
運動会や掃除の時間、いつも一生懸命に取り組む先輩方の姿が、とてもかっこよかったです。
これからの中学校生活でも、笑顔を忘れず頑張ってください。
そして時々、母校のことを思い出してください。
本当にありがとうございました。
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 短く素直な表現 | 感謝と応援を中心に、2分以内でまとめる |
| 使う場面 | 在校生代表の送る言葉・卒業生代表の答辞 |
立場ごとに言葉づかいやトーンを少し変えるだけで、聞く人の印象は大きく変わります。
あなたの役割に合わせて、最も自然に伝わる言葉を選んでください。
感動を生む祝辞を作るためのポイント
祝辞をより印象的で心に残るものにするには、内容の構成だけでなく、伝え方や言葉の選び方も大切です。
この章では、聞く人の心を動かすための5つのポイントを紹介します。
「感動」は特別な言葉ではなく、誠実な気持ちから生まれます。
心に響く言葉を選ぶ方法
感動を与える祝辞の基本は、聞く人に寄り添う言葉選びです。
難しい表現や形式的な言葉よりも、短くて温かみのある言葉が印象に残ります。
たとえば、「頑張りましょう」よりも、「あなたならきっと大丈夫です」という言葉のほうが、優しさが伝わります。
| 比較例 | より伝わる表現 |
|---|---|
| これからも努力を続けてください。 | これからも自分のペースで前に進んでください。 |
| 失敗しても諦めないで。 | 失敗も大切な経験として受け止めてください。 |
| 一生懸命頑張りましょう。 | 少しずつでも、今日より明日へ進めば大丈夫です。 |
“上から話す”言葉ではなく、“寄り添う言葉”が印象に残る祝辞をつくります。
エピソードを交えて個性を出す
実際に見た子どもたちの頑張りや行事でのエピソードを取り入れると、祝辞にリアリティが生まれます。
たとえば、「運動会で声を掛け合っていた姿」「合唱で力を合わせた瞬間」などを一言入れるだけで、場面が浮かびます。
“自分の目で見た出来事”を話すと、聞く人は自然と引き込まれます。
| エピソードのタイプ | 使い方の例 |
|---|---|
| 行事での努力 | 「運動会での全力の走りが今でも目に浮かびます。」 |
| 日常の姿 | 「朝の挨拶を欠かさなかった皆さんの姿勢は本当に立派でした。」 |
| 仲間との絆 | 「互いを思いやる気持ちが、学級全体を明るくしていました。」 |
形式と流れを意識して話す
祝辞は自由に話せるスピーチではありますが、構成の流れを意識するとまとまりが出ます。
基本構成は「お祝い → 成長 → 感謝 → 未来への言葉」。
特に中盤で「成長」と「感謝」をつなげると、感情が自然に高まります。
聞き手が想像しやすいよう、文を短く区切りましょう。
| NG例 | 良い例 |
|---|---|
| 長文で一気に話す | 一文を短くし、間を取る |
| 同じ言葉を繰り返す | 類語を使って自然に言い換える |
| 感情を抑えすぎる | 落ち着いた口調で気持ちを込める |
長すぎない構成を意識する
祝辞の長さは、短すぎると印象が薄く、長すぎると退屈になってしまいます。
3〜5分以内を目安に、原稿用紙で2枚半程度に収めましょう。
文を削るときは、「自分が本当に伝えたい部分」だけを残すと自然に整理されます。
“言葉の数より、思いの濃さ”が大切です。
緊張しない話し方のコツ
式典では緊張してしまうものですが、いくつかの工夫で落ち着いて話せます。
| コツ | 具体的な方法 |
|---|---|
| ゆっくり呼吸する | 話す前に深呼吸を2回行う |
| 最初の一言を暗記する | 「ご卒業おめでとうございます」だけを暗記しておくと出だしが安定 |
| 目線を動かす | 特定の人ではなく、会場全体を見るように意識 |
少しの準備で安心感が増し、声にも自信が生まれます。
「うまく話す」より、「心を込めて話す」ことを意識するだけで、印象は大きく変わります。
祝辞のNG例と避けたい表現集
どんなに内容が良くても、言葉の使い方や話し方を誤ると、聞き手に違和感を与えてしまうことがあります。
この章では、よくあるNG例を紹介しながら、より自然で印象の良い表現に直すコツをお伝えします。
「何を言うか」だけでなく、「どう伝えるか」が祝辞の印象を決めます。
長すぎる・難しすぎるスピーチ
卒業式は多くの人が参加する式典のため、長すぎる祝辞は聞き手の集中力を奪ってしまいます。
また、難しい言葉や抽象的な表現が多いと、小学生には意味が伝わりにくくなります。
| NG例 | 改善例 |
|---|---|
| 「皆さんの未来には数多の試練が待ち受けていますが…」 | 「これからも、挑戦を楽しみながら進んでください。」 |
| 「自己の研鑽を怠らず精進を重ねてください。」 | 「学びを続け、自分を信じて進んでください。」 |
| 5分を超える長文スピーチ | 3分以内で簡潔にまとめる |
「難しい言葉」よりも「伝わる言葉」を選ぶのが、聞く人の心を動かす第一歩です。
個人名・比較表現に注意
祝辞では、特定の児童の名前や家庭に関することを話題にするのは避けましょう。
また、「誰よりも優れていた」「一番頑張っていた」などの比較表現も控えるのがマナーです。
| 避けるべき表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| 「○○さんはとても優秀でした。」 | 「みんなが力を合わせて素晴らしい成果を出しました。」 |
| 「○○くんが代表で…」 | 「代表として立派に役割を果たした児童がいました。」 |
| 「一番努力していた人」 | 「互いに励まし合いながら努力してきた皆さん」 |
このように言い換えることで、特定の人を強調せず、全体への敬意が伝わります。
時事ネタ・宗教・政治に関わる話題
祝辞はあくまで学校行事の公の場です。
個人的な意見や、宗教・政治・時事に関する話題は避けるのが原則です。
また、冗談や笑いを取る表現も、式の雰囲気によっては不適切に受け取られることがあります。
| NG例 | 言い換え例 |
|---|---|
| 「最近のニュースでも取り上げられているように…」 | 「これからの時代を担う皆さんに期待しています。」 |
| 「政治や社会の変化の中で…」 | 「社会が変わっても、人とのつながりを大切にしてください。」 |
| 「冗談交じりのスピーチ」 | 「温かく落ち着いた口調で語る」 |
卒業式の目的は、感謝と祝福を共有すること。
それ以外のテーマを入れずに、明るく穏やかな雰囲気を保ちましょう。
以上を意識すれば、誰が聞いても心地よいスピーチになります。
「聞いていて心が温かくなる」——そんな祝辞が、最高の贈り物です。
まとめ|心に残る「卒業おめでとう」をあなたの言葉で
ここまで、祝辞の構成や例文、注意点を見てきました。
最後に、改めて大切なポイントを整理しながら、「自分らしい祝辞」を完成させるヒントをお伝えします。
祝辞は“正しく話す”ものではなく、“想いを届ける”ものです。
卒業生に残る“たった一言”を意識する
長い文章よりも、最後の一言が心に残るものです。
「あなたたちならきっと大丈夫です」「未来を信じて進んでください」といった短いメッセージが、卒業生の背中を優しく押します。
話すときは、その一言を大切に心を込めて伝えましょう。
| 印象に残る締めくくりの例 | 効果 |
|---|---|
| 「皆さんの未来が、光あふれるものになりますように。」 | 前向きで希望に満ちた印象を与える |
| 「ここでの思い出を胸に、新しい一歩を踏み出してください。」 | 卒業の節目を感じさせる |
| 「これからも、自分らしく輝いてください。」 | 自立と成長へのエールになる |
自分の言葉で伝えることが何より大切
インターネットや例文集にはたくさんの参考になる文章がありますが、最も響くのはあなた自身の言葉です。
感謝、誇り、希望——その気持ちを自分の言葉で表現すれば、自然と感動が生まれます。
完璧を目指すより、“心のこもった言葉”を大切にしましょう。
| 伝わる祝辞の共通点 | ポイント |
|---|---|
| 短くても温かい | 長さよりも誠実さ |
| 個性が感じられる | 体験や思い出を一言入れる |
| シンプルな構成 | 「お祝い → 感謝 → 未来への言葉」を基本に |
卒業式は、人生の中でも特別な節目の日。
その場で贈る言葉は、子どもたちにとって一生の記憶に残るものになります。
“ありがとう”と“おめでとう”をまっすぐ伝えることが、何よりの祝辞です。

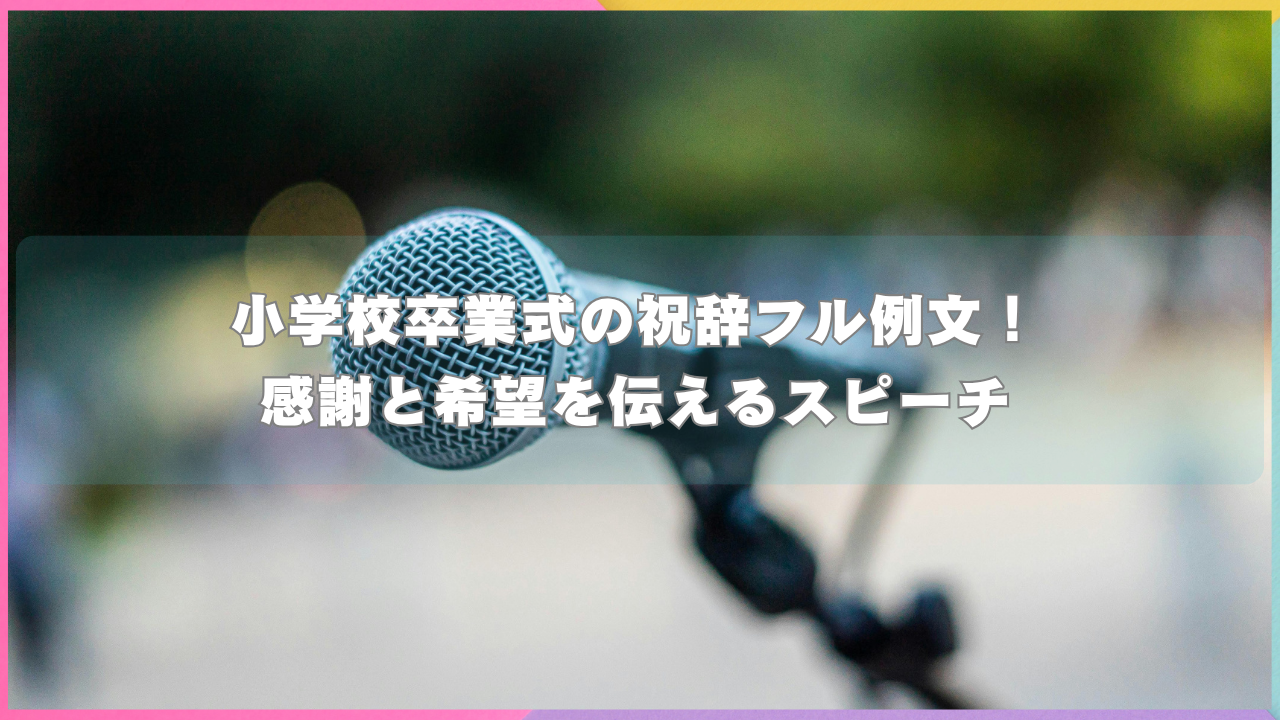

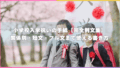
コメント