11月にお礼状を書くとき、「どんな時候の挨拶を入れるべき?」「ビジネスと個人で表現を変えた方がいい?」と迷う方は多いのではないでしょうか。
11月は秋から冬への移り変わりを感じる時期であり、紅葉、小春日和、立冬など、この季節ならではの言葉が文章を彩ります。
本記事では、11月にふさわしいお礼状の基本構成とマナーを押さえながら、すぐに使える例文を上旬・中旬・下旬に分けて紹介します。
さらに、ビジネス向けと個人向けのフルバージョン例文も用意しましたので、シーンに合わせてそのまま活用できます。
この記事を読めば、相手に誠意が伝わるお礼状を自信をもって書けるようになります。
11月のお礼状にふさわしい表現とは
11月のお礼状を書くときにまず悩むのが、「どんな言葉で季節感を表すか」という点です。
この章では、11月らしい自然の描写や、文章に使いやすい表現を整理してご紹介します。
さらに、漢語調と口語調の違いを知っておくと、ビジネスでも個人でも表現の幅が広がります。
11月らしい季節感を伝える言葉
11月は秋が終わりに近づき、冬の気配を感じ始める季節です。
そのため、紅葉や落ち葉、小春日和、木枯らしといった言葉がよく使われます。
こうした言葉を入れることで、お礼状にやさしさや温かみを添えることができます。
| 表現 | 意味・ニュアンス | 使用例 |
|---|---|---|
| 晩秋の候 | 秋の終わりを感じる時期 | 晩秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。 |
| 向寒の候 | 冬に向かって寒さが深まる頃 | 向寒の候、体調を崩されていませんか。 |
| 小春日和 | 11月の穏やかな晴れの日 | 小春日和が心地よい季節となりました。 |
| 暮秋の候 | 秋も暮れようとしている頃 | 暮秋の候、貴社ますますご清栄のことと存じます。 |
自然の移ろいを描写するだけで、お礼状はぐっと印象的になります。
漢語調と口語調の違いと使い分け
11月のお礼状に使う挨拶には「漢語調」と「口語調」の2つがあります。
漢語調は「晩秋の候」「立冬の候」のようにかっちりした表現で、主にビジネスシーンで使われます。
口語調は「落ち葉舞い散る季節となりました」「日が暮れるのが早くなりましたね」のようにやわらかい言葉で、個人宛てにぴったりです。
| 種類 | 特徴 | 例文 |
|---|---|---|
| 漢語調 | 形式的・フォーマル | 深秋の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 |
| 口語調 | やわらかく親しみやすい | 木枯らしが吹き始める季節となりましたが、お元気でお過ごしですか。 |
相手やシーンによって表現を切り替えることが大切です。
ビジネスには漢語調、個人には口語調を意識すると安心です。
お礼状の基本構成と書き方の流れ
お礼状はただ感謝を伝えるだけでなく、相手に丁寧な印象を残す大切な手紙です。
ここでは、お礼状を書くときに守りたい基本の流れを解説します。
この順番を意識すれば、誰でも自然で読みやすいお礼状を書けるようになります。
冒頭文と時候の挨拶
最初の部分では「拝啓」などの頭語に続けて、時候の挨拶や相手の健康を気遣う言葉を添えます。
これにより、文章全体が柔らかく、相手に寄り添った雰囲気になります。
| 要素 | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| 頭語 | 文の冒頭に置く決まり文句 | 拝啓 / 謹啓 |
| 時候の挨拶 | 季節を感じさせる言葉 | 晩秋の候、皆様ますますご健勝のことと存じます。 |
| 相手を気遣う言葉 | 健康や生活への思いやり | お変わりなくお過ごしでしょうか。 |
冒頭は「礼儀」と「温かさ」を兼ね備えることがポイントです。
感謝の気持ちを伝える本文の書き方
続いて、本題である「感謝」をシンプルに伝えます。
相手がしてくれた具体的な行為に触れると、より誠意が伝わります。
たとえば「先日はご多忙の中お時間をいただき、誠にありがとうございました」などが基本です。
| 状況 | 感謝の伝え方 |
|---|---|
| 贈り物をいただいた場合 | 「このたびは心のこもったお品を頂戴し、厚く御礼申し上げます。」 |
| 食事や招待を受けた場合 | 「先日は楽しいお時間をご一緒させていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。」 |
| 仕事上のサポートを受けた場合 | 「日頃より多大なお力添えを賜り、心より御礼申し上げます。」 |
「ありがとうございました」だけで終わらせず、具体性を加えると信頼が増します。
結びの挨拶で好印象を残すコツ
最後に、今後の関係を大切にしたいという気持ちを添えるのが「結びの挨拶」です。
季節の変化に触れたり、相手の健康を気遣う言葉で締めくくると、印象がやわらぎます。
| 結び表現 | 使うシーン | 例文 |
|---|---|---|
| 体調を気遣う | 個人・ビジネス共通 | 寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。 |
| 発展を祈る | ビジネス | 貴社のますますのご繁栄を心より祈念しております。 |
| 親しみを込める | 個人向け | 季節の変わり目ですので、お体を大切になさってください。 |
結びの言葉は「また会話を続けたい」という意思表示です。
11月のお礼状【例文集:上旬・中旬・下旬】
11月のお礼状は、上旬・中旬・下旬で選ぶ表現や雰囲気が少しずつ変わります。
ここでは、ビジネス用と個人用に分けて例文をたっぷりご紹介します。
そのまま使えるフルバージョン例文も用意しましたので、安心してご活用ください。
11月上旬のお礼状例文
11月上旬は紅葉が見ごろを迎える季節です。
秋らしい景色を描写すると、相手にやわらかい印象を与えられます。
| 種類 | 例文 |
|---|---|
| ビジネス用(短め) | 暮秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先日は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 紅葉の美しい季節、皆様のますますのご発展を心より祈念いたします。 |
| 個人用(短め) | 紅葉が鮮やかに色づく季節となりました。 このたびは温かなお心遣いをいただき、心より感謝申し上げます。 朝晩の冷え込みも増してまいりましたので、どうぞお体を大切になさってください。 |
| ビジネス用(フルバージョン) | 拝啓 晩秋の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。 有意義なお話を伺うことができ、今後の業務に大変参考となりました。 木々が色づく季節、貴社の皆様におかれましても、益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 敬具 |
| 個人用(フルバージョン) | 拝啓 落ち葉舞い散る季節となりました。 このたびは心のこもったお品を頂戴し、誠にありがとうございました。 さっそく家族でいただき、心温まるひとときを過ごすことができました。 季節の変わり目で体調を崩しやすい頃ですので、どうぞご自愛くださいませ。 またお会いできる日を楽しみにしております。 敬具 |
上旬は「紅葉」や「落ち葉」をキーワードに取り入れると効果的です。
11月中旬のお礼状例文
11月中旬は立冬を過ぎ、冬の入り口を意識した表現が合います。
| 種類 | 例文 |
|---|---|
| ビジネス用(短め) | 立冬の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。 先日はご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。 向寒のみぎり、どうぞご自愛くださいませ。 |
| 個人用(短め) | 立冬を迎え、寒さが増してまいりました。 先日はご親切なお心遣いをいただき、本当に感謝しております。 風邪など召されませんよう、どうかお体にお気をつけください。 |
| ビジネス用(フルバージョン) | 拝啓 立冬の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 先日は温かなお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 日々のご支援に心より感謝申し上げます。 寒さが一層深まってまいりますが、皆様のご健勝と貴社のさらなるご発展を祈念いたしております。 敬具 |
| 個人用(フルバージョン) | 拝啓 暦の上では冬を迎えましたが、まだ秋の名残を感じる日もございます。 このたびは温かなお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 いただいた品は家族皆で大切に使わせていただいております。 日増しに寒さが厳しくなります折、どうぞご健康にご留意くださいませ。 敬具 |
中旬は「立冬」「向寒」を入れると季節感が強まります。
11月下旬のお礼状例文
11月下旬は冬の訪れが本格化する時期です。
年末を意識した言葉を加えると、より自然な締めくくりになります。
| 種類 | 例文 |
|---|---|
| ビジネス用(短め) | 深秋の候、平素より格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。 師走に向けてご多忙の折、どうぞご自愛くださいませ。 |
| 個人用(短め) | 日が暮れるのが早くなり、冬の訪れを感じる頃となりました。 先日は温かなお心遣いをいただき、感謝しております。 寒さ厳しい折、お体を大切になさってください。 |
| ビジネス用(フルバージョン) | 拝啓 深秋の候、平素は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 先日はご多忙の中、丁寧なご対応をいただき感謝申し上げます。 年末に向けてご多忙のことと存じますが、皆様のご健勝と貴社の益々のご繁栄を心より祈念いたしております。 敬具 |
| 個人用(フルバージョン) | 拝啓 冬の気配が日に日に濃くなる頃となりました。 このたびは素敵なお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 いただいた品は大切に活用させていただいております。 年の瀬も近づきお忙しいことと存じますが、どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。 また来年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。 敬具 |
下旬は「深秋」「師走に向けて」といった言葉が締めにふさわしいです。
シーン別で使える11月のお礼状フレーズ
お礼状は、相手や場面に合わせた言葉を選ぶことで、より気持ちが伝わります。
この章では、ビジネスと個人宛てそれぞれに使える便利なフレーズを整理しました。
結びの言葉や一文フレーズを組み合わせるだけでも、立派なお礼状になります。
ビジネスで活用できる結びの言葉
ビジネスのお礼状では、相手の健康や会社の発展を願う表現を入れるのが基本です。
やや堅めの文章にすることで、誠実さと信頼感を示すことができます。
| シーン | フレーズ例 |
|---|---|
| 相手の健康を気遣う | 向寒のみぎり、くれぐれもご自愛くださいませ。 |
| 今後の関係を大切にしたい | 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 |
| 会社の発展を祈る | 貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 年末を意識した表現 | 年の瀬も押し迫り、何かとご多忙のことと存じますが、皆様のご健勝をお祈りいたします。 |
ビジネスでは「誠実さ」を感じさせる言い回しが鍵です。
個人宛てに使えるあたたかい表現
個人宛てのお礼状は、少しくだけた表現で親しみを込めると相手に喜ばれます。
季節感のある言葉や、体調を気遣う一文を添えると心が伝わります。
| シーン | フレーズ例 |
|---|---|
| 季節感を添える | 小春日和のやわらかな日差しが心地よい季節となりましたね。 |
| 相手を気遣う | 朝晩の冷え込みが厳しくなりましたので、どうぞお体を大切になさってください。 |
| 再会を願う | またお目にかかれる日を心待ちにしております。 |
| 年末を意識した表現 | 今年も残りわずかとなりました。どうぞ健やかに新しい年をお迎えください。 |
個人宛てでは「やわらかさ」と「親しみやすさ」を意識するのがおすすめです。
11月のお礼状で気をつけるマナーと注意点
お礼状は「感謝の気持ち」を伝える手紙ですが、マナーを誤ると逆効果になることもあります。
ここでは、11月にお礼状を書く際に注意しておきたいポイントをまとめました。
気をつける点を押さえておけば、より心のこもった手紙に仕上がります。
季節感と相手への気遣いのポイント
11月は秋から冬へと移り変わる時期なので、文章の中に「寒さ」や「紅葉」などを入れると自然です。
ただし、あまりに季節感が強すぎると形式ばった印象になることもあります。
相手がどんな環境にいるかを意識し、ほどよい表現を選ぶことが大切です。
| よくあるNG | 理由 | 改善例 |
|---|---|---|
| 「寒さ厳しき折」ばかりを多用 | 11月はまだ冬本番ではなく、不自然に感じられる | 「紅葉の美しい季節」「落ち葉舞う季節」などで柔らかさを出す |
| 季節感を入れない | 形式的で無機質な印象になる | 「小春日和の心地よい日が続いております」と添える |
相手の状況に合わせて、自然な季節感を盛り込むことが一番の心配りです。
敬語の使い分けと失敗しやすい例
お礼状では「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」を正しく使う必要があります。
特にビジネスシーンでは、間違った敬語は信頼を損なう原因になりかねません。
| 間違いやすい表現 | 誤用例 | 正しい表現 |
|---|---|---|
| 「ご苦労さまです」 | 上司や取引先に使うのは不適切 | 「お疲れさまでございます」 |
| 「拝見させていただきました」 | 「拝見」と「させていただく」が二重敬語 | 「拝見いたしました」 |
| 「いただければ幸いです」 | ややカジュアルで曖昧 | 「賜れましたら幸甚に存じます」 |
二重敬語や身内言葉は特に注意が必要です。
迷ったときはシンプルで基本的な敬語を選ぶのが安全です。
構成を守れば初心者でも安心
文章の流れが乱れていると、読み手にとってわかりづらくなります。
「冒頭 → 感謝の本文 → 結び」という基本の型を守れば安心です。
事前に使いたい「時候の挨拶」や「結びの言葉」をピックアップしておくと、スムーズに書けます。
| 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 冒頭 | 時候の挨拶と相手への気遣い | 晩秋の候、皆様お健やかにお過ごしのことと存じます。 |
| 本文 | 感謝の言葉を具体的に伝える | このたびは心のこもったお品を頂戴し、誠にありがとうございました。 |
| 結び | 健康や発展を祈る言葉 | 寒さ厳しくなってまいります折、どうぞご自愛くださいませ。 |
「基本構成+相手に合った言葉選び」で、誰でも失敗のないお礼状が書けます。
まとめ|11月のお礼状で心を伝えるために
ここまで、11月にふさわしいお礼状の表現やマナー、そして具体的な例文を紹介してきました。
改めて整理すると、お礼状は「時候の挨拶」「感謝の言葉」「結びの一文」の3つを押さえるだけで十分形になります。
そこに11月らしい季節感を加えれば、相手の心に残る一通が仕上がります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 時候の挨拶 | 紅葉や立冬、小春日和など11月らしい言葉を選ぶ |
| 感謝の言葉 | 「ありがとうございました」だけでなく具体的な出来事を添える |
| 結びの一文 | 健康や発展を祈る表現で、相手を思いやる |
「どんな場面で」「誰に送るか」によって、表現を調整するのも大切です。
ビジネスにはフォーマルな漢語調、個人には親しみやすい口語調を選べば安心です。
今回の例文をベースに、ご自身の気持ちを一文添えると、よりオリジナリティのあるお礼状になります。
11月は寒さとともに温かい気遣いが嬉しい季節です。
ぜひ手紙を通じて、思いやりを届けてみてください。

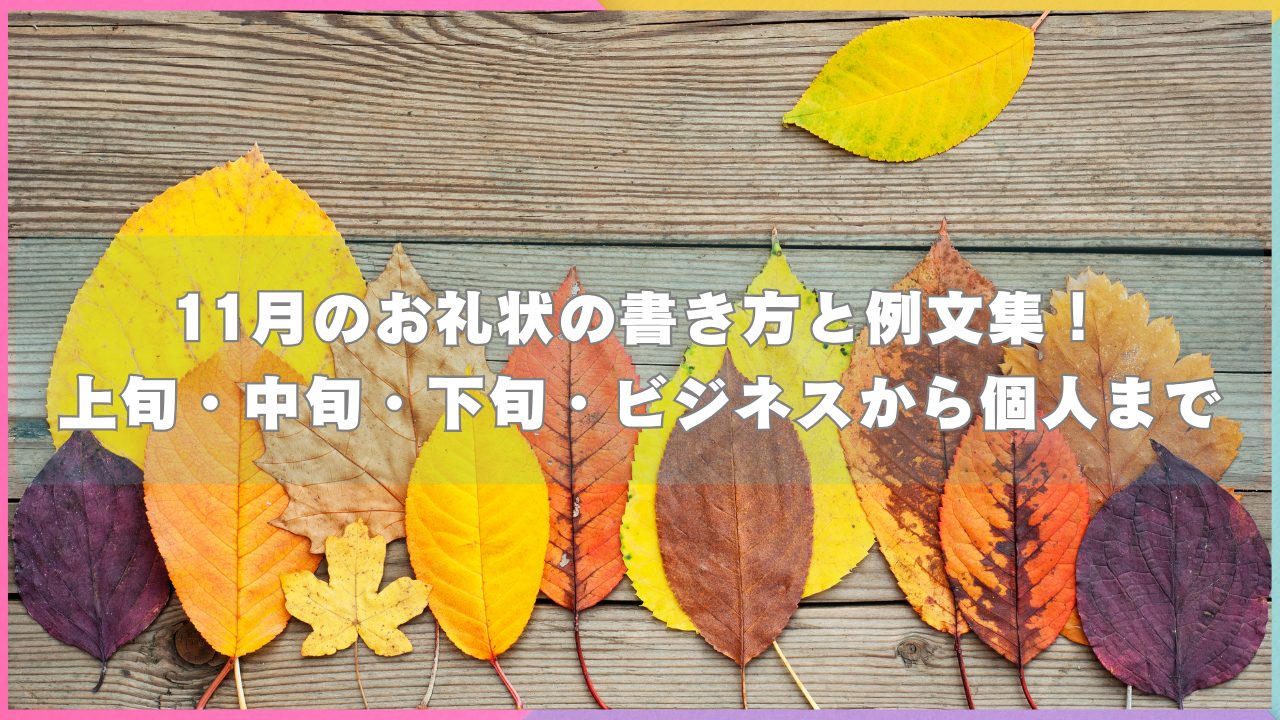
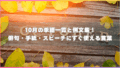
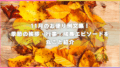
コメント